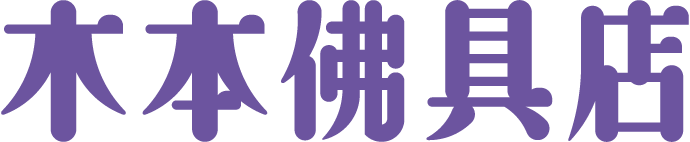2023.02.22
神酒の口製作秘話?
我が家に残る古い神酒の口。
40年以上の前の物。
毎年暮れになると我が家にこれを届けてくださる方がありました。明治生まれの女性でした。
ずっと保管してあり、私としても気になる物で、時々箱を開けて眺めていました。

「誰にも作り方を教えない」と言っておられた物で、
その方が亡くなってからは頂く事は当然無く、先の物をずっと仕舞い込んでいました。
店の建て替えなどで、処分するタイミングもあったと思うのですが
出来なかったんでしょうね、祖母も。
私が4歳とか5歳とか本当に小さい頃、
一度だけご自宅で仕上げ作業しておられるのを見た事があって、
誰にも教えないけどウチの母になら教えたいと話しておられたのも横で聞いてた。
でも母が習う事は無く、その女性も亡くなれた。
私は仕事で少し水引を扱うので、水引細工には興味があり、
特に婚礼品の細工を見て習ってみたいと思うようになりました。
2021年に素敵な水引細工が作れる通信講座を見付け、思い切って受講しました。
習ってみると、普段念珠修理などでやっている結びや茶道の仕覆の結びとか、
やっぱり似てると気が付き、楽しく学ぶ事が出来ました。
↓ かなり頑張って作ったお正月飾り。
なんかですね、右肩に付いてる松とか、
「何でこんな物作れるんだ、変態!」って思う程なんですよ。
自分で自分に感動して褒めてしまいますよ。

色々作っていくと、やっぱり気になるのは「我が家に残る古い神酒の口」。
ちょっと習った今なら、もしかしたら自分でも作れるんじゃない?!
と一人盛り上がり始め、再現を試みる事に。
でもまぁ、始めてみると難しいのよ。
講座で習った結びとは全て手が逆でこんがらがってしまい、ドツボにハマる。
一瞬、自分が何をやっているのか分からなくなる程。
何度天を仰ぎ、唸った事か。
でもひたすら結び、手に慣れさせ、覚える。
習った方の手でやろうかとも思ったけど、調べてみると、
昔は小学校の授業で神酒の口を教わったりしていたようで、
左右や上下は、きっと何か意味がある。明治生まれの人ならば
日常の作法に陰陽があって、恐らく意味も分かっていて、身に付いた物
として作っていたはずだ。これを作った人にも教えてくれたお母さんや
おばあちゃんが居たはずだ。だから、残された物に習う。
寸法の割り出しも、折り形のバランスも難しい。
でも何とか形となる。試作品。内側の小さい方。
お手本(外側の大きい方)は40年以上前の物で、明治生まれの女性が作った物。

なんかさぁ、迫力と佇まいが違うのよ。違うでしょ?!
家族は「よぉ作ったねぇ!」と褒めてくれたけど、
どうにも越えられない壁を感じてしまうのよね・・・。
それに、材料が違うせいか整えなれない箇所があってどうにもならない。
更に手直しをして、改良してなんとかサマになるように。


私、コレを作りたかったんだろうな、と最近しみじみ思う。
今となって思うけど、色んな物事を見聞きさせて貰い、実は刺激的な子供時代を送ってたんだなぁ、と。
もの凄い手間なんだけど、今これを作る価値はあるだろうな、と思っています。
色々画像も検索してみたけど、地方によって様々が形があり、受け継がれているのが
わかりました。私が作ったのは今のところ例が無く見当たらないので、
明治時代の富山型、と言おうかしら。
あまり数は作れないので細々と作って行きますよ、私は。
そうそう、インスタに載せていたら、
全日本宗教用具協同組合のブログ記事に画像載せてもいいですか?
と問い合わせがきたのでOKしました。ありがとうございます。
沢山の方にご覧頂けたら幸いです。
#水引 #水引細工 #神酒口 #雄蝶雌蝶 #神酒すじ
#全日本宗教用具協同組合
#富山市丸の内 #仏壇富山 #木本仏具店