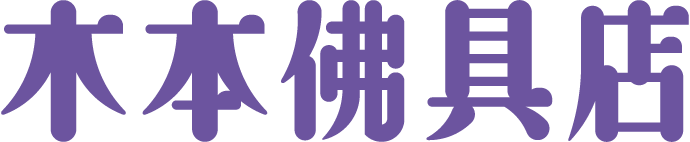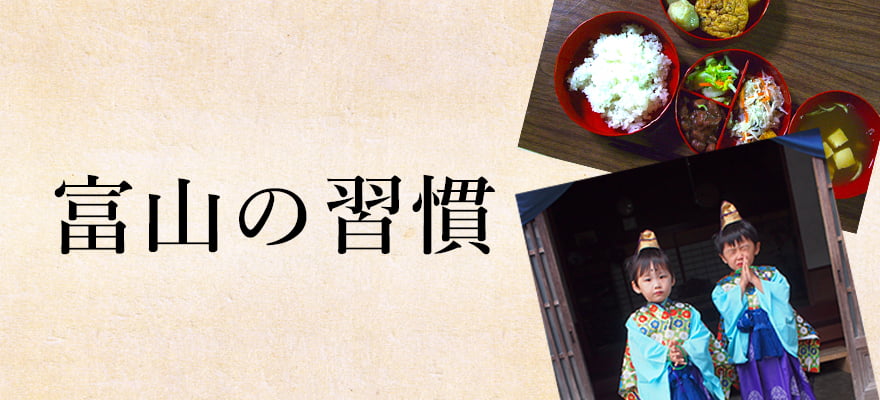富山の習慣
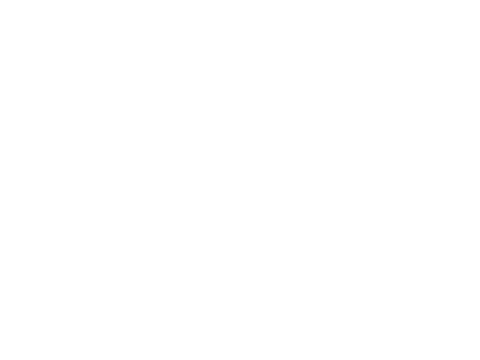
富山の仏事の習慣
富山ならではの
習慣をご紹介します。
みたま

弔事の際に食べられる黒豆のおこわ。法要の際の仏前に供えたり、直会の席での御膳や引き出物で頂く事も多いですね。
北陸地方では馴染みのあるおこわですが、他の地方ではあまり見られないようです。漢字は「御霊みたま」を充てると思われます。
おけそく

法要の際のお供えする丸餅の事を「おけそく」と言います。漢字だと「御華束」又は「御華足」。
主に浄土真宗で用いる仏具で、六角や八角の「供笥くげ」の別称が「けそく」と呼ばれていて、お餅を供える専用の仏具の事。仏具を指していたものが、上に供えられた餅の事もそのように呼ばれるようになった物と思われます。
浄土真宗の法要では菓子や果物よりもお餅を供えます。
いとこ煮

報恩講(親鸞聖人のご命日のおまいり)の際に食される小豆の入った汁物・煮物です。冬の味として食卓に上がるご家庭も多いと思います。
小豆の他、大根、人参、里芋、牛蒡、蒟蒻、豆腐などを柔らかく煮て醤油又は味噌で味を調えます。
報恩講をお勤めされるお寺さんでは必ずと言ってよいほど作られます。
お寺さんごとに、そのお家ごとに中に入れる具材や味付けも様々です。
地蔵盆(地蔵まつり)

西日本を中心に7月~8月にお勤めをされる。地域でおまいりされている所も多く、児童会や町内会で行事を催す所が多いようです。
富山市内ではいたち川沿いの延命地蔵尊が有名で、7月にお勤めされている様子。
この地蔵まつりの風習は常願寺川以東ではあまり聞かないので、全国的に見て富山市が最も東になるのかもしれません。
画像は当店がある富山市丸の内の地蔵尊まつりで、丸の内1丁目、2丁目、3丁目が合同でお護りしています。
毎年8月23日にお寺さんにお願いし、一同で読経、法話をいただき、一年間に3町内でお亡くなりになられた方の御供養をしています。
仏壇まいり

結婚式の日、白無垢姿や打掛姿の花嫁さんが新郎の家へ赴き、ご仏前、ご先祖様へ結婚の報告をする「仏壇まいり」の習慣があります。
現在では少なくなっていますが、結婚式の前におまいりの日を設けておられるお家は結構あるようです。
この習慣があるため、富山の女性は「念珠(数珠)」を花嫁道具のひとつとして準備されるのが定着しています。
浄土真宗が多い地域のため水晶やサンゴを用いた白の二輪が好まれますが、宗派により形は各々ございますので、ご結婚の際にお念珠を用意される方は、嫁ぎ先のお家の宗派を確認される事をお勧めしております。
和蝋燭

法要のお勤めの際には、和蝋燭を用います。左側2本が「棒型」で、浄土真宗以外の宗派で用います。
回忌を問わず、ほとんどの法要で白色を用いる事が多いです。
右側の蝋燭上部の裾が広がっているのが「碇型(又はバチ型)」と呼ばれる形で主に浄土真宗で用います。
一般的に七回忌までは白色、十三回忌以降では朱色を用います。特に五十回忌、百回忌法要ではお目出度い行事として金色を用います。
使用する色は地域によってもお寺様のお考えによっても異なる事がございますので、法要の際には使用する蝋燭の色、大きさをご確認ください。
元旦のおまいりや、花嫁さんの仏壇まいり等、御一家のお目出度い日にはぜひ朱色の蝋燭を灯しておまいりなさる事をお勧めします。
なお金色の蝋燭は金箔を押しますので、ご注文を頂いてから3~4日程のお時間を頂戴しております。
熨斗袋

御香典は「黒白」、御仏前(初七日以降の法要)は「黄白」を使用するのが富山では一般的です。
五十回忌以降の法要には「紅白」のものを用います。