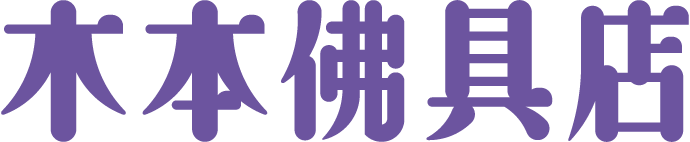よくある質問(仏事)
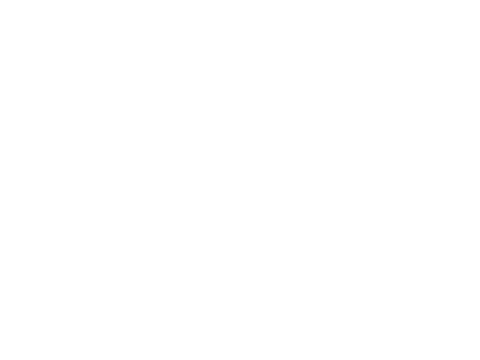
仏事・法要について
法要で使うローソクの型や色を教えてください。
一般的に浄土真宗ではバチ型、他の宗派では棒型のローソクが使われます。 また一周忌と三回忌、七回忌は白のローソクを、以降は赤のローソク、五十回忌には金箔のローソクで法事をされることが多いです。 (お寺様の考えもありますので、お寺様の相談されてみてください)
仏様へのおまいりに欠かせない「香(こう)・燭(しょく)・華(げ)」って何ですか?
仏様へのおまいりに欠かせない「香(こう)・燭(しょく)・華(げ)」。 「香」は線香や焼香、「燭」は蝋燭の灯、「華」はお花です。最近では「線香が煙たい」「蝋燭の油煙でお仏壇がくすむ」 「花立に入れた水の湿気で仏壇が傷む」等を理由に献ずる事を嫌煙されたりもしますが、日々のおまいりに大切な要素です。 当店では香りの良いお線香、油煙を抑えた蝋燭や、燃焼時間の短い蝋燭なども取り揃えております。 お花を活ける際に何種かの花、色があれば、白い花を高い位置に配するのが仏花ではでは良いとされています。 棘のある花は禁花(バラ、アザミなど)なので活けるのは控えましょう。
普段は三具足で飾っているのですが法事の時は五具足の仏具を飾ったほうがいいのですか?
法事や報恩講などの行事の際はあるならば五具足で飾ってください。三具足しかない場合は普段と同じように三具足でかざってください。
法事の際のお寺様へのお布施はどのくらい?
明確な指標はございません。ご親戚同士で相談の上、決められることが多いようです。 封筒の表書きはお布施と書き、白の封筒または回忌にあわせて水引のついたのし袋を用います。三十三回忌までは黄白、五十回忌は紅白を用います。
白木のお位牌はどうしたらいいですか?
四十九日の法要のあと、お寺様が持って帰られます(ただし、地域によって異なる場合がございます)。 四十九日以降は法名軸またはお位牌を安置しておまいりしてください。
よそのお宅のお通夜や葬儀に参列する際、相手のお家の宗派に合わせておまいりしなければならないですか?
基本的に仏式のお勤めであれば、自分のお家の宗派の作法でおまいり(焼香や念珠の持ち方など)で大丈夫です。 ただ、おまいりの作法等を先に案内された場合は、その指示に従ってください。
念珠(数珠)はどういう物を持てばいいですか?
よく「二輪」とか「二重」と言われているタイプのものが各宗派で使われる念珠(数珠)で、それぞれ仕立てが違います。 特に浄土真宗について言えば、男性は一重の片手タイプの物を、女性は白の二輪タイプを用います。
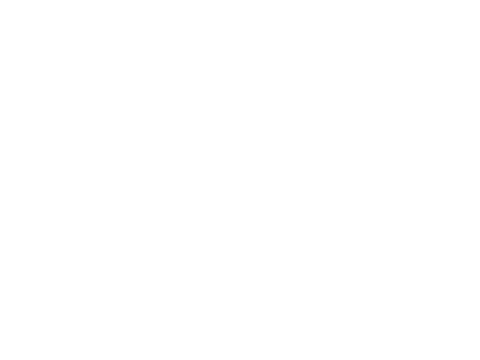
飾り方
法名軸が沢山あるのですが、全部掛けられません。どのようにしたらいいですか?
沢山の掛軸がある場合は、その方が亡くなられた命日に掛けてさしあげ、それ以外の日はしまっておいてもよいかと思われます。 三十三回忌や五十回忌を過ぎた方のものは、しまっておかれることが多いです。多数のご先祖がいらっしゃる場合は過去帖に書き写し、おまいりしてください。
ご飯は3つお供えしないとダメなの?
仏飯はいくつお供えするかは宗派によっても異なります。浄土真宗の場合、日常でも法要でも3つのお仏飯が必要です。
お水やお茶はあげなくてもいいの?
お水やお茶をお供えするのは浄土真宗以外の宗派のお給仕です。 浄土真宗ではお供えしません。
神棚を置く方角はどこがいいですか?
おまいりをする人が西、もしくは北に向かっておまいりするように設置されるのが良いとされています。
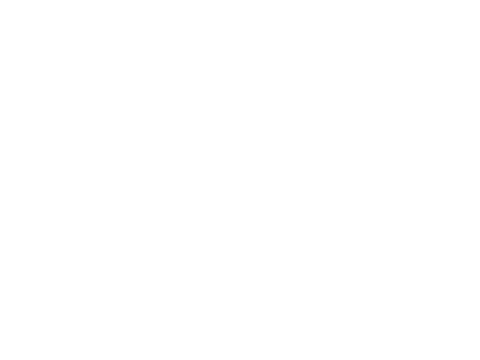
お仏壇の修理
お仏壇の箔洗いはどれくらいの年数が経つとすればいいの?
経年による劣化で金箔色が悪くなったり、彫物や障子の組子が落ちる等の傷みが多く見られると、修復を考えられるお客様が多いです。 購入、前回の箔洗いから30~50年経った頃にご相談をお受けする事が多いです。
ご本尊の掛け軸が古くなり、全体に黒くて仏様のお姿も見えなくなってる。新しくしたほうがいい?
数十年~100年の年数が経つと、掛軸が黒くなることはよくございます。 仏様のお姿が見えないのなら、いっその事新しい御本尊をお迎えしようとお考えになるお客様もいらっしゃいますが、当店ではそれはお奨めしておりません。 永い年月、ご家族と共にあったご本尊です。表装直しをしてまた次の世代の方へ継承されることをお奨めしております。