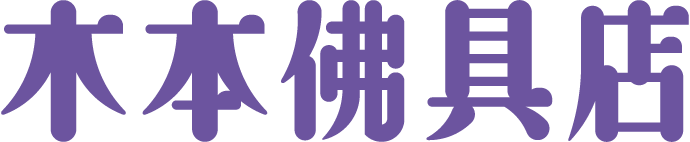2021.10.14
オンライン研修会に参加からの自分勝手な雑感。
先日、当店も加盟している全日本宗教用具協同組合の研修会に参加しました。
毎年、秋に京都で開催されている研修会ですが、今年はオンラインで受講。
歴史とか民俗学の研究者の講演は毎回楽しみで、今回もお二方のお話を聞く事が出来ました。

今回、興味深かったのは、
①神様と松、火の話。
②先祖を祀るようになったのは江戸時代。定住率が上がったからだ。
③年忌法要。七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌。なんで7と3?
の3つの話題に喰い付いてしまいました。以下、自分勝手な雑感。(長い)
①火は神様の乗り物。お正月、玄関に飾る門松は年神様に来て頂くための依り代なのは知っていましたが、
門松やしめ縄、前年のお札をお焚き上げする左議長は神様にお帰り頂くため。
お盆にお墓からご先祖を迎えに行く時は、墓で提灯に火をともし提灯を提げてお連れしたもの。
帰りは仏壇・盆棚前、玄関で提灯をともし、またお墓まで。これも火を乗り物としている。
これは子供の頃に母の故郷・長崎県の五島列島のお盆の迎え火・送り火がそうだった。
祖父母に「提灯の中にはご先祖様が入ってるから転んだらダメ!」って言われた覚えがあります。
関東各地?のお盆では、玄関先で焙烙を使ってお先祖が迷わずに帰ってこれるように、
また帰ってもらう時にも火を焚く。京都の大文字焼き。
ご先祖様にとっても火は乗り物なのだ。
富山に住んでいると土地柄お盆にそんな事をする習慣が殆ど無いので実感ありませんが。
お松籟をするお宅は川の橋の上でされています。
左義長はまだありますが、色々厳しくなって、昔のように城址公園で火を焚くことはなくなってます。
それにしても、お墓まで送り迎えするか、玄関先で送り迎えするか。
墓地が徒歩圏内に有るかどうかでやり方が変わってきますよね。
提灯だと蝋燭、昔だと油火の小さな炎で。焙烙だと少し大きな炎で。
遠くからでも見えるようにの目印って事か?
ああ、そうか。
提灯は子孫直接お出迎え、お見送りの図。
焙烙は旅館の送迎バスみたいなものか。
送迎の乗り物(きゅうりの馬と茄子の牛)は用意するので、ご先祖は自分で乗って帰ってきてねって。
乗り物を遣わし、玄関で出迎える子孫はさしずめ旅館の女将のようなものか。
大文字の送り火は、団体さんの大型バスみたいなもん?!(叱られろ。)
スタイル違えば準備しなくてはならない物も違ってくるのは当然。
五島列島の実家ではきゅうり茄子は無かった。墓地で花火するのは未だに謎だけど。
②一般で先祖を祀り始めたのは定住化率が上がった江戸時代になってから。
会場で日本人が定住化したのは稲作が始まった弥生時代じゃないのか?っていう質問があったけど、
それまでの稲作は今のような田んぼでなく、泥地での稲作。
流されたらおしまいで、土地にこだわり無く、各地を転々としていた。
江戸時代になって土木技術が向上。畔のある田んぼが出来、河川の堤防を築くための治水工事も進む。
収穫量も上がり、安心して住める土地も増える。
また農閑期には治水工事などの仕事に従事することで賃金を得る事ができたので、定住化が進んだとの事。
戸籍管理は神社が氏子としてまとめ、(大字という地名が名残とか。)
移動は寺院が発行する証文がなければ出来なかった。
定住化してやっと先祖を祀る事が始まった。
なので、天皇家や公家ならば代々の家系図や墓もあるが、庶民の家だと墓でも家系図でも、どんなに古くても
寛永(1624~1643)だっけな?元禄(1688~1703)だっけな?そこまでしか遡れない、残ってないとの事。
我が家も初代が亡くなったのが天明3年(1783年)。
2代目の子がそれより前の安永2年(1773年)8月5日と6日に二人が
立て続けに亡くなっているのが過去帳見ると書いてある。
初代の親が1700年前後に生まれと推定すると納得出来る話ではある。
ちなみに、庶民が葬儀を行うようになったのは中世らしい。(うる覚え)
禅宗の僧侶が同僚僧侶の死を弔う為に行こなっていた儀式を庶民に転用されたのではないか、との事。
それまでは家族が死んでも儀式をして弔ったりもせず、その辺に放っておかれたり、
ただ埋められたりしただけでおしまいだったんですね。
葬儀も何も無ければ墓もなく、先祖も気にしないとなれば年忌法要など執り行うはずもなく。
日本人が先祖を祀るようになって300年程度って事なのか?!
③法事も不思議なんですよね。
三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌。
なんで末尾7と3?これもずっと謎でしたが講演で少し触れられて、
どうも地蔵本願経というお経の内容が元になっている。
7が最強の数字で、7,17、27大事。
その大事な7に7足した 7+7=13 17+7=23 27+7=33
13、23、33も大事という事らしいです。
(小学校一年生の足し算間違ってる訳では無くて、数え年みたいな事だと思われます。)
興味あるのでもう少し詳しく知りたい。
二七日とか七七忌(四十九日)とかも「7大事発想」なんだよね?
この話を聞いていた方で、3,7,13,17,23,は素数なのも気になるよね!って
言ったおられる人もいて、(数学嫌いなのでそれは思い浮かばなかった。)増々気になります。
そういえば何年も前に「冥土の旅はなぜ49日なのか」っていう数学者の人が書いた本を
買いましたよ。でも最初の数ページで脱落したのを思い出しました。
成り立ちの過程を研究したような話も大好きだし、知識が増えるのも楽しいし、
地域ごとの習慣風習も面白いし、こんな話はもっと聞きたいです。
で、学生時代、「民俗学」「日本の宗教」「世界の宗教」、
サボらずにもっと真面目に授業出とけば良かったです。。。
「日本の宗教」の授業で先生が言っていた
「日本人は先祖崇拝だけしてればそれで安心なんです」と言っていた事、
あの授業ではこの言葉だけが印象的でずっと頭から消えず今日に至っていましたが、
その導入部分が今回の研修会で聞いた話しなんだろうな。
少しスッキリしました。
後で先生の名前検索してみるか。今日はコレで終了。
長くてごめんなさい。
研修会参加させて頂いてありがとうございました。