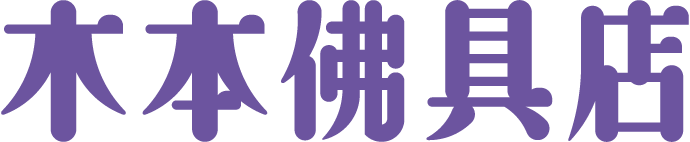2018.10.06
おまいりと共にある郷土の料理 第2回
おまいりと共にある郷土の料理 第2回
●「報恩講」と「いとこ煮」
富山の郷土料理に「いとこ煮」があります。
富山では報恩講の時に頂く精進料理で、郷土食であり、行事食です。
秋から冬、大根や里芋が美味しい頃に食卓に上がるお家もあるでしょう。
全国的にも「いとこ煮」はあると 思いますが、かぼちゃと小豆を一緒に煮た「煮物」を
「いとこ煮」と言うことが多いようです。
12月の冬至の日によく食べられている料理です。
味付けは醤油ベースであったり、シンプルに塩味、砂糖やハチミツで甘く煮たりと様々。
我が家のいとこ煮はこれです。

材料は、小豆、大根、人参、ゴボウ、里芋、厚揚げ、こんにゃく、味付けは味噌です。
野菜たっぷりで作ると美味しいです。全国的ないとこ煮は「煮物」としてのお惣菜のようですが、こちらでは汁物で、お味噌汁の位置づけです。
けんちん汁の小豆入り、豚汁の豚肉抜きの小豆入り、と言えば味の想像がつき易いでしょうか?
我が家では一度に10人前くらいを大鍋で作って、家族のほか、店のスタッフや
知人にも配っています。
大人になってから「美味しい」と思えるようになりましたが、子供の頃には、
ちょっと物足りない感じの地味なもの、と思っていました。
「報恩講」は浄土真宗の開祖・親鸞聖人の祥月命日の法要で、
本願寺派では新暦の1月16日、大谷派では旧暦の日付の11月28日を命日としています。
浄土真宗において、一年で一番大事な法要が報恩講と言われています。
富山でも秋から冬に、各真宗寺院において、門徒を集めて報恩講の行事が勤められます。
我が家の縁借りのお寺さんでも報恩講があったのでおまいりに行ってきました。
お勤めには近隣のお寺の住職さんもこられ、「正信偈」を上げられます。
おまいりに先立ち、参列の門徒さんたちには、昼食のお斎(とき)の席に通され、
お食事を頂戴します。こちらが、その時のお料理です。精進料理です。

一汁三菜の献立です。ごはん、いとこ煮、お煮しめ、煮豆、お酢あえ(なます)、
白菜の漬け物です。
親鸞聖人は小豆が好物だったと言われており、小豆を使った料理が献立に入ります。
大根や里芋の煮物は本当に味がよく染みて美味しかったです。
こちらのお寺さんのいとこ煮は我が家の具沢山とは違って、焼き豆腐、
小豆、そしてたっぷりと柚子の皮が散らされて、本当に香りの良いお汁で
美味しかったです。
初めて頂いた時は、見た目もお味も「ウチのいとこ煮と全然違う!
こっちの方が好きかも!」という衝撃がありました。
それぞれのお家、お寺で具材も違うもんなんだなぁ、と。
余談ですが、こちらの紅白なます、富山では「お酢あえ」とか「おすわい」と
呼んでいるのですが、甘めに煮つけた厚揚げを細かく切ったり
ほぐしたりしたものも一緒にあえています。
こちらのお寺のはさらにヒジキとこんにゃくも入った豪華ななますで美味しいのですが、
ちょっとびっくりだったのが、我が家の本寺さんの所で食べたなますと同じ具材、
よく似た味付けだった事です。本寺さんと縁借りのお寺さんは亡くなった先代坊守が
姉妹だったと聞いているので、坊守さんのご実家のお味なのかな、と思った次第です。
お寺さんでは、門徒の奥さん方の協力を得ながらこれらのお料理を作っておられます。
大根などは味が染みた方が美味しいですから、前日からお手伝いに入って準備しておられるそうです。
話しは前後しますが、一般家庭でも報恩講のお勤めをしています。
月まいりの時に報恩講のおまいりも一緒にしてもらったり、誰かの年忌法要の時に一緒にお勤めしたり。
「普段の月参りは近所の縁借り寺に来てもらうけど、報恩講だけは年1回必ず
本寺さんが厳重に来られる」と言う話も結構聞きます。
昨年の秋、主人の実家でおばあさんの13回忌とひいおじいさんの50回忌法要があったのですが、
その時にもお二方の法要の先に報恩講のお勤めをされました。
和ろうそくはお寺でも在家でもバチ型の朱色の和ろうそくを使います。

今回、いとこ煮や報恩講の精進料理について色々調べましたが、
昔は、報恩講にお寺さんを家にお呼びして、親類も招いてお勤めをするという事が
年に一度のハレの行事で、家族総出で掃除をし、一年で一番のご馳走を作り、
一番良い御膳を出してきて、お酒も振る舞い、正月よりも豪華なご馳走食べる事が出来る日であったようです。
それは富山に限らず、近県の新潟、石川、福井、岐阜でも同じであったようです。

(画像は京都・清涼寺境内にある湯豆腐のお店「竹仙」の精進料理。)
昔、当店に務めていた木地職人は、仏壇作る作業もしていたけど、
本職はご膳用のお椀を作る職人で、父が子供の頃、昭和30年代はお椀の木地を売る卸しもしていた、と聞いています。
それだけ、「講」や祭りなどで、大勢が寄り合って食事を共にする機会が多く、
まとまった数の御膳や器を一般家庭が準備して持っていた。
蓮如上人が発展された「講」という組織のお陰で、お椀の需要があったのだと、
父が話します。
私の自宅にも、今でも大量の御膳、お椀、皿などの器類、徳利、盃、
こんなにあってどうしようか、と思うほど残っています。
曾祖父母が戦後から集めていった物です。(最近、結構捨てました。)

(画像は我が家のお雑煮。元旦のお雑煮にだけ使用している「稲穂に雀」のお椀。
祖母が昭和22年にお嫁に来た時には既にあった、と言っているので相当古い。
大事に使ってはいますが、熱いお汁を注ぐため、色も変色。漆が剥離してしまい
もう使えないお椀もある。箱もボロボロで汚いですが、もしかしたら我が家で
一番大事に使っているお椀かもしれません。)