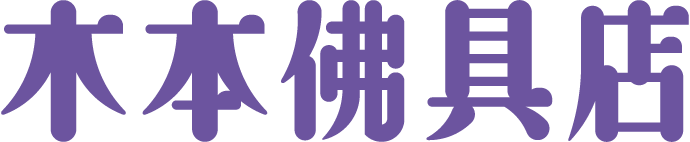2016.07.09
お盆に向けて提灯をかざりました。お盆の思い出。
お盆に向けて提灯を飾りました。

新盆の方へのお供えとして贈り物にされたりします。
撫子や木槿、桔梗などの夏の草花が描かれたものが多いです。
提灯を沢山飾るのは特に九州地方。
私の母は長崎県・五島列島の出身ですが、祖父母の新盆の時には、親戚、知人から沢山の提灯が届けられました。
新盆の時には、お墓に提灯を飾るための木枠を組んで、提灯をお供えに持ってお参りに来られる方を迎えます。いつ誰がお参りに来られるか分からないので家族はお墓で待機しています。墓地に行って木枠があると「あのお宅は今年新盆なんだな」と分かります。
富山に居ると祖母から「朝早くお墓参りに行くように」と言われるのですが、九州では夕方陽が沈んでからお墓に出かけます。どこの家でもそうなので集落の共同墓地は大賑わい。お母さんたちの井戸端会議、久しぶりの同級生との再会も墓地、子供たちも集まって花火をしたりと、「兎に角、九州に帰るとお墓参りが楽しかった」という思い出があります。
お盆の夕刻のひとときをお墓で過ごし、家路に着く時、手提げ提灯の蝋燭に火を灯し、「火が消えないように、転んだりせんように、気を付けて歩くとよ~。提灯にはご先祖様が入っておられるからね。」と言われながら街灯も無い暗い道を帰りました。帰ったらお仏壇に蝋燭を灯し、仏間に飾った提灯も点灯します。8月15日の夕刻には仏壇の前で提灯の蝋燭を灯し、手に提げてお墓へ向かいます。
これが「迎え火・送り火」だったんだなぁと気が付いたのは30代になってから。
我が家は浄土真宗なのでお松籟をしたりはしませんが、夏、提灯を見かけると、「火袋の中にはご先祖様がいらっしゃる」と懐かしい気持ちになります。
余談。子供のころ父に「ウチのお墓でも花火しようよ~。」と誘ってみたところ、「何ゆーとんがけっ」と呆れられました。これも思い出。